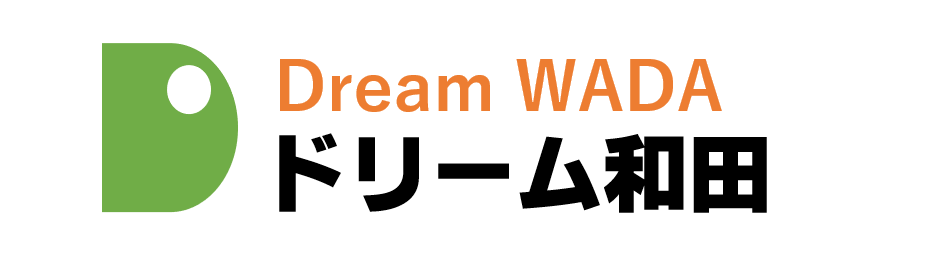昨日は【多量・微量要素の追加】に関する堆肥の濃度についての話。
今回は【土壌構造の発達】
堆肥がどのようにして土をフカフカにするか。
フカフカになる要因としては、団粒構造の形成が挙げられます。
しかしながらほぼ全て堆肥にはその力が残っていないと考えています。
まず団粒構造の形成には有機物や粘土鉱物を核として、有機物が分解されたときにできる糊のようなものや関わっています。
畑に残る植物残渣や鉱物がこの糊や菌糸などにくっつけられ、まとめ上げられることによって団粒を形成。
そしてその団粒化が地表から地面深くへ進んでいくことによって団粒構造が形成されます。
畑で糊なんてみたことない。という方も多いと思うので、
昨年行った団粒構造の素を探る実験。
割りばしにキノコ菌を接種して通気できる黒のビニール袋に入れて数週間。そして取り出す。


割りばしも立派な有機物。袋の一番下になっていた割りばしにはドロドロとした粘性物質がたっぷり。
堆肥とはある程度‘’分解し終わったもの‘’。
堆肥をつくる過程でできた貴重な粘性物質はたんぱく質であるため堆肥の中で再び分解され、無機化。
気化したり、雨水によって流されていき、完成した堆肥にはその残りしかありません。
堆肥が土をフカフカにするというのは堆肥そのものの材質だったり、申し訳程度の未分解の有機物のおかげかもしれないというのが今のところの見解です。
ではどうしたら団粒構造を実現できるのか。
団粒構造は奥が深いのでまた来週。
昨年の秋バックホーで耕盤破壊した畑の整地作業。
乗り心地はよくない。